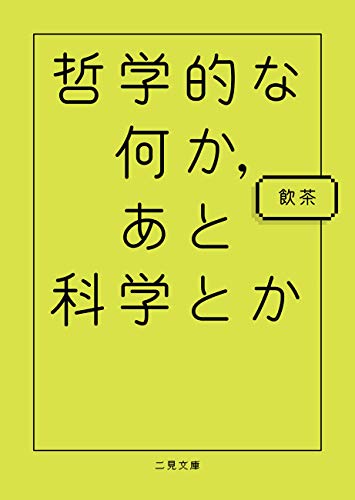- ものごとを深く広く知るためにはどのような視点を得ることが重要でしょうか。
- 実は、世の中の摂理、つまり哲学や科学かもしれません。
- なぜなら、これらの研究は、絶えず人の思想と世界の捉え方をアップデートしていくために不可欠なものだからです。
- 本書は、哲学を明朗に語る飲茶さんによるエッセイ的1冊です。
- 本書を通じて、この世界をどのように知るのか、その人の挑戦や視点について、思いを馳せることができます。
確実だと思えることほど・・!?
飲茶(やむちゃ)さんは、哲学と科学の複雑な世界を、驚くほど分かりやすく私たちに届けてくれる稀有な書き手です。本名は非公開ながら、その親しみやすいペンネームが示すように、堅苦しい学問の世界に新しい風を吹き込んでいます。
もともとはシステムエンジニアとして働いていた彼が、なぜ哲学や科学の解説者になったのか。
それは「難しいことを簡単に説明したい」という純粋な想いからでした。
専門書を読んでも理解できない、でも知りたいという多くの人の気持ちを誰よりも理解していたからこそ、彼の文章には温かさがあります。
『史上最強の哲学入門』をはじめとする著作は、まるで友人と喫茶店で話しているような親近感で、カントやニーチェといった大哲学者たちの思想を解き明かしています。
単なる知識の羅列ではなく、「なぜその人がそう考えたのか」「それが現代の私たちにどう関係するのか」を常に意識した解説は、多くの読者に「哲学って面白い!」という発見をもたらしてきました。
科学の分野でも同様で、量子力学や相対性理論といった難解なテーマを、身近な例えと共に紐解いていく手法は、彼独自のものです。
「三千年を解くすべを持たない者は闇の中か、未熟なままに、その日その日を生きる」
ゲーテのこの言葉を引用して、飲茶さんは私たちに大切なことを問いかけます。
それは、自分の思考の枠組みを意識できているかということです。
普段の生活で、私たちはどれくらい「なぜそう思うのか」を立ち止まって考えているでしょうか。相手の意見をそのまま受け入れたり、テレビやネットの情報を疑わずに信じたり、「みんながそう言っているから」という理由で判断してしまうことは少なくありません。
でも、それって実はとても危険なことかもしれません。なぜなら、私たちが「当たり前」だと思っていることの多くは、実は過去の誰かが作り上げた考え方や、特定の時代背景から生まれた常識に過ぎないからです。
飲茶さんが本書で伝えたいのは、まさにこの点です。
哲学や科学の歴史を知ることで、「どうして人はそう考えるようになったのか」「その前提は本当に正しいのか」を見抜く力を身につけることができる。
三千年の知恵に学ぶことで、私たちは「その日その日を生きる」だけの存在から脱却できるのです。
飲茶さんが科学に魅力を感じるようになったきっかけは、とても印象的なエピソードから始まります。それは、ニュートリノという素粒子の発見物語でした。
当時の科学者たちは大きな問題に直面していました。計算上は存在するはずなのに、あまりにも小さすぎて観測できない粒子があるというのです。普通なら「そんな小さい粒子があるはずがない」と諦めてしまうところでしょう。
ところが科学者たちは諦めませんでした。「確実は不可能だ」と言われながらも、彼らは驚くような実験を考案します。巨大な水槽を用意し、もしニュートリノが水分子とぶつかれば「カチンって感じで、ちょっとだけ光が出る」はずだと仮説を立てたのです。そして実際に実験を行った結果、「その光が特定の頻度で観測できることが確認され、ニュートリノという新粒子があることが証明された」のです。
ここで飲茶さんが驚いたのは、科学者たちの発想の転換でした。直接見ることができないなら、間接的な証拠で「あったことにしてしまう」というのです。光が出たからニュートリノが存在する。でも、本当にニュートリノそのものを見たわけではない。あくまで「そう考えると辻褄が合う」から「存在する」と認めたに過ぎないのです。
これは、よく考えてみると驚くべきことです。私たちが「科学的に証明された」と信じているものの多くが、実はこうした間接的な推論に基づいているということ。飲茶さんにとって、これは科学という営み自体が思っていた以上に曖昧で、ある意味では「信念」に近いものだという発見でした。
この体験が、飲茶さんに「確実だと思っていたものほど、実は不確実なのかもしれない」という視点をもたらしたのです。
私たちが唯一できることとは!?
ニュートリノの発見から科学の面白さを知った飲茶さんですが、さらに深く学んでいくうちに、もっと根本的な問題に気づくことになります。それは、私たちが「絶対に正しい」と思っている数学や科学の土台が、実は意外に不安定だということでした。
例えば、数学の世界では「公理」と呼ばれる基本的なルールがあります。これは「証明する必要のない、明らかに自明な法則」として扱われているものです。ユークリッド幾何学でいえば、「平行線は絶対にまじわらない2本の線(平行線)を引くことができますよ〜」というのも、長い間、疑いようのない当たり前のこととされてきました。
ところが、よく考えてみると不思議なことに気づきます。「1つ重大な問題点を見逃してはならない。公理と呼ばれる基本法則でも、証明はされていないのだ」ということです。
1830年頃、数学者のガウスがこの問題に挑んだ結果、驚くべきことが分かりました。「平行線の公理」が成り立たない幾何学も作ることができる、ということです。しかも、「幾何学として矛盾が発生しない」どころか、まったく新しい幾何学体系が作られることを発見したのです。
つまり、私たちが「絶対に正しい」と信じていた数学の基礎でさえ、実は選択肢の一つに過ぎなかったのです。
これは、先ほどの「常識を疑う」という話をさらに深刻にしたものかもしれません。
公理の不安定さを知った飲茶さんは、さらに深い問題に直面することになります。それは数学だけでなく、私たちの思考そのものが抱える根本的な限界についてでした。
この事件以降、数学の理論体系は「絶対的な真理の記述」ではなくなり、「ある一定の公理をもとに、論理的基礎の書籍で作られた推論物」とみなされるようになったのです。そして100年後、ゲーデルという数学者が決定的な発見をします。
ゲーデルは「我々が、どんなにうまく公理を選択して無矛盾に見える理論体系を構築しようとも、その理論体系の無矛盾を自分の理論体系の中で証明することは不可能である」ことを証明したのです。
つまり、理論体系は完全にトドメをさされたということでした。
これは恐ろしい発見でした。私たちがどれほど論理的に正しいと思える体系を作っても、それが本当に正しいかどうかを、その体系の中からは証明できないというのです。
そして飲茶さんは、この数学の限界が私たちの日常にも当てはまることに気づきます。
「我思う、ゆえに我在り。この世のすべてが、信じられないものであろうとも、それを『疑っている何者かが存在すること』は、絶対的な事実なのだ」
デカルトの有名な言葉の本当の意味がここで見えてきます。
疑って、疑って、疑いつくしても、最後に残るのは「疑っている自分の存在」だけ。これが、私たちが確実に言えることの限界であり、同時に出発点でもあるのです。
曖昧な言葉の中を生きて!?
「我思う、ゆえに我在り」で確実な出発点を見つけたデカルトでしたが、飲茶さんはそこからさらに深い問題を掘り下げていきます。それは、私たちが普段当たり前に使っている「言葉」や「定義」そのものの曖昧さについてでした。
例えば、数学で「A=B、B=Cならば、A=C」というのは論理的思考の結果だと思われがちです。しかし、よく考えてみると不思議なことに気づきます。
そもそも「A=B」、つまり「AはBである」というのはいったいどういうことでしょうか。何をもって「A=B」と判断できるのでしょうか。
飲茶さんは鋭い指摘をします。世の中に完全に同じものなんてあるのだろうか。いや、仮に自分で「AとBがまったく同じだった」としても、それを言葉で表現した瞬間に「A」と「B」という別の言葉で言い換えているだけではないか。本質的には「A=A」ということにすらならない。
「ボクらが『A=Bである。だから〜』といようとき、そこには確実に『推論』という操作があるのだ。それが論理的思考の正体である」
この指摘は、私たちの思考の根っこを揺さぶります。
論理的だと思っていることの多くが、実は言葉の定義に依存した「推論」に過ぎないということです。
そして、この問題はもっと身近なところでも起こります。私たちは日常的に「自転車」という名前を何の疑いもなく使っていますが、果たして「自転車」とは何でしょうか。
飲茶さんは面白い思考実験を提示します。「自転車」からハンドルを取ったらどうなるか。今度はタイヤを取ったらどうか。ペダルを取り外したら。一つずつ部品を外していくと、いったいどの時点で「自転車」でなくなるのでしょうか。
「『自転車』というものを取り外したわけでもないのに、そこから『自転車』というものは消えてしまった。逆に、取り外した部品を一個ずつ『自転車』に戻しても『自転車』が現れる」
これは深い洞察です。「自転車」という存在は、独立した確固たるものではなく、「複数の部品の構成によって、発生した性質(システム、仕組み)」について、人間が便宜的に名前を付けただけなのかもしれません。
つまり、「『自転車』という存在は、独立した確固たるものではなく、暫定的なものなのだ」ということです。そして、これは自転車だけの話ではありません。「原子核と電子」という集まりによって、便宜的に「鉄」や「金」という名前を付けたに過ぎない。
「原子核と電子をバラバラにしてしまったら、もうそこには『鉄』なんかない」のです。
私たちが「これは○○だ」と確信を持って言っていることの多くが、実は便宜的な定義や暫定的な名前に過ぎないという現実。
これは、冒頭で触れた「常識を疑う」ということの、もっと根本的な意味を教えてくれているのかもしれません。
飲茶さんのご著書については、こちら「【自他を抱きしめるために?】あした死ぬ幸福の王子――ストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」|飲茶」の1冊もぜひご覧ください。とてもおすすめです。

まとめ
- 確実だと思えることほど・・!?――不確実で、曖昧なものごとかもしれません。
- 私たちが唯一できることとは!?――「それは本当かな?」と疑う自分が確実に存在することを認めることです。
- 曖昧な言葉の中を生きて!?――実は、当たり前に使われている言葉自体も曖昧なものであるのだから、わたしたちに確固たる信じるべきものごとはないのかもしれないのです。だから、私たちは、自分の感覚を活かして、その信じられるものごとを見つけていくことが良いのかもしれません。